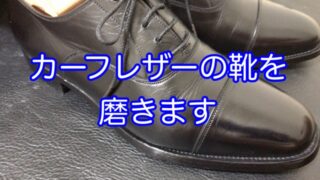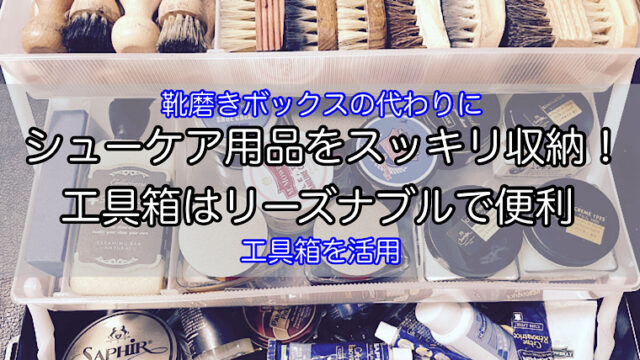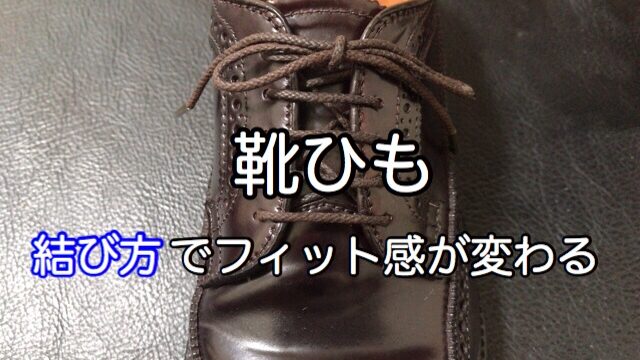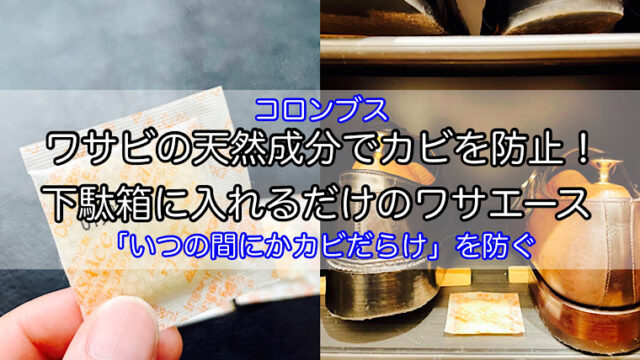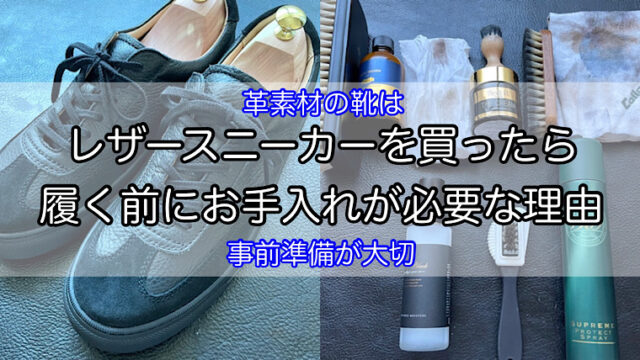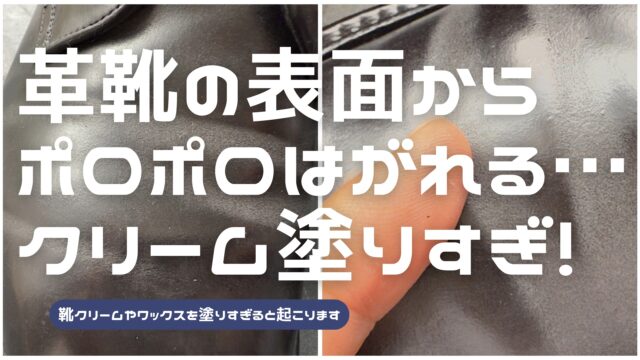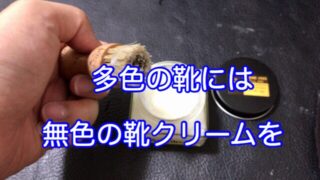オイルドレザー靴のお手入れ方法を解説!必要な道具は?ノーメンテはNGです

本記事ではオイルドレザーのお手入れについて手順を追いながら紹介していきます。
オイルドレザーとはその名の通り、油をたっぷりと含ませた革。
丈夫で乾燥しにくい特長を持ちます。
革靴の美しさとは、形状はもちろん、革自体が放つ独特の風合いによるところも大きいですよね?
革が持つ美しい風合いというのは、革に含まれている水分や油分が適度に保たれることで表れます。
オイルドレザーは油を多く含んでいるため、革のみずみずしさが長期間キープされます。
ある程度の期間はお手入れしなくても革の風合いを楽しむことが可能。
ですが、オイルドレザーもまったくメンテナンスしないと、いずれ乾燥することに…。
革の乾燥は百害あって一利なし。
乾燥した革は独特の風合いが失われ、ひび割れが発生しやすくなります。
ひび割れを防ぐため、オイルドレザーの靴でもしっかりとお手入れする必要がありますよ。
(2026/02/02 21:59:22時点 楽天市場調べ-詳細)
オイルドレザーは油をたっぷり含んだ丈夫な革
オイルドレザーとは皮をなめす工程でふんだんに油を染み込ませ、出来上がりの革のしなやかさを向上させた丈夫な革のこと。
製造する過程で油分を十分に染み込ませています。
そのため、水をはじきやすく撥水性に優れるという特性があります。
オイルドレザーを使用した靴は丈夫さと水への強さを合わせ持つのです。
つまり、アウトドアシーンなどの比較的過酷な環境でも気兼ねなく履くことが可能。
ですが、いくらオイルドレザーの靴が丈夫だからといって、ガシガシとハードに履いた後のメンテナンスを怠ってしまうと革の乾燥が進行します。
そうなると、せっかくのオイルドレザーの特長である、油分が含まれているゆえのしなやかさと撥水性が失われることに…。
ただの乾燥した革になってしまうのです。
したがって、オイルドレザーの靴であっても他の革種の靴と同様に、
- お手入れをして栄養を補給する
必要があります。
乾燥したオイルドレザーはかさついて見るも無残な状態
オイルドレザーにも栄養補給が必要ということがわかったところで…。
今まさに、栄養補給が必要なオイルドレザーの靴をご覧ください。
それが…。
これです。

レッドウィング(RED WING)の短靴。
遠目から見ても革が乾燥していることがわかりますね。

近づいてみると余計に顕著。
オイルドレザー本来の深く濃い色と、革が乾燥して色が薄くなっている箇所が混在しています。
実はこれ、メンテナンスせずに履き続けてこうなったというわけではありません。
ジェイソンマークのシュークリーナーを使用して、靴を洗った後の状態です。
洗剤と水を使ってブラシでゴシゴシ革をこする工程を経ると、いくらオイルドレザーとはいえ乾燥します。
当然ですね。
今回は、こちらの乾燥した革靴に油分を補給していきます。
長期間メンテナンスしていないオイルドレザーの乾燥の場合でも、今から紹介する手順と同じ方法でケアできます。
オイルドレザーに油を入れ直す方法を解説
オイルドレザーであっても、油分補給の方法は通常の革種の靴磨きとあまり変わりません。
まずは作業工程を見てみましょう。
- 靴のホコリを払い落とす
- 靴に付いた汚れや古い靴クリームを落とす
- 革に油分を与える
- 油分をブラシでなじませる
- クロスで磨く
大きく分けて全5工程。
普通の革靴と手順は変わらないですね。
ホコリを払い落とす
まずは、馬毛のブラシでブラッシングして細かいホコリや砂を払い落とします。

ホコリを落としておくと、この後の汚れ落としや油分補給がホコリに邪魔されなくなります。
より効率良くケアができます。
靴に付いた汚れや古い靴クリームを落とす
続いて、靴用クリーナーで汚れや古いクリームを落とす工程に移ります。
今回ケアする靴は、すでにジェイソンマークの洗剤で洗っています。
ですが、靴上に洗剤成分が残っている可能性を加味して、念のためクリーナーを使用します。
使うのはこちらのクリーナー。

ブートブラックシルバーラインのツーフェイスローションです。
ツーフェイスローションは靴用のクリーナーで、水性クリーナーと油性クリーナーの2種の成分を含んだ、いわばハイブリッドクリーナー。
水汚れは水性クリーナー、油汚れは油性クリーナーにそれぞれ溶け込むので、どちらの種類の汚れも1度に落とせる優れもの。
ツーフェイスローションをクロスに取り…

靴のアッパーを拭きます。

靴に汚れが残っていると、この後の油分補給の効果が薄れてしまいます。
汚れが油の浸透を阻害してしまうためです。
しっかりと汚れを落としましょう。
ですが、ゴシゴシこするのはNG。
革を傷めてしまいます。
あくまで優しく。
クロスでなでるようにです。
革に油分を与える
汚れを落としたら、次は革に栄養を与えましょう。
栄養補給剤はこちら。

レッドウィングのオールナチュラルレザーコンディショナー。
レッドウィングのオイルドレザー用のペースト状クリームでオールナチュナルと読んで字のごとく、すべて天然成分で構成されています。
天然の、
- ミンクオイル(動物性油脂)
- ビーズワックス(蜜蝋)
- パインピッチ(松ヤニ)
を配合。
レッドウィングではオールナチュラルレザーコンディショナー以外にも、オイルドレザーに油分を与える、
- ミンクオイル
も販売しています。
どちらを使用するか迷ってしまうのですが、僕がオールナチュラルレザーコンディショナーを選択したのには理由があります。
(2026/02/02 21:59:22時点 楽天市場調べ-詳細)
オールナチュラルレザーコンディショナーを使う理由
オールナチュラルレザーコンディショナーとミンクオイル、どちらを使用しても油分補給効果はあるのですが…。
どこが違うのかというと…。
オールナチュラルレザーコンディショナーは100%天然成分から作られているためコストが高いものの、天然成分のみを使っている分、環境にも革にも優しい製品。
革への浸透性が良好です。
加えて、パインピッチが放つ松の香りが使用時の気分を高めてくれる効果もあります。
一方のミンクオイルは、有機溶剤を主成分としてロウ・シリコンを加えることで防水効果を高める効果があり、比較的低価格です。
- ミンクオイルはロウやシリコンが入っているため防水効果が高い
- オールナチュラルレザーコンディショナーは革への浸透性の良さや革の保護に優れる
僕としては、オイルドレザーのしなやかさや革本来の美しさという点を重視したかったので、オールナチュラルレザーコンディショナーを選択しました。
どのように仕上げるかで使う靴クリームを選べるのはとてもありがたいです。
オイルドレザー靴にオールナチュラルレザーコンディショナーを塗る
オールナチュラルレザーコンディショナーのペーストを手に取ってみると、こんな感じ。

スッと手に取れる柔らかさがあります。
革の乾燥した箇所を中心にペーストを塗り込んでいきます。

付けすぎ注意です。
ミンクオイルは、塗りすぎると革を必要以上に柔らかくしてしまいます。
目安としては、
- もうちょっと塗った方が良いかな
くらいのところで1度止めておきましょう。
後日、革の様子を確認して、
- まだ革が乾燥していると感じたらペーストを付け足す
といった具合がおすすめです。
油分をつぎ足すことは簡単にできますが、油分を抜くことは簡単ではないですからね。

ウェルト部分の乾燥も激しいので、ここにもしっかりとオールナチュラルレザーコンディショナーを塗り込みます。
(2026/02/02 21:59:22時点 楽天市場調べ-詳細)
オールナチュラルレザーコンディショナーを塗った後の状態は?
オールナチュラルレザーコンディショナーを塗り終わった革靴の状態がこちら。

革に潤いが与えられて、色も濃くなっています。
ずいぶん乾燥が解消されました。
革へ与えた油分をブラシでなじませる
革に油分を塗り込んだら、塗った油分を革へまんべんなくなじませます。
そう。
ブラッシングです。
使うのは豚毛ブラシ。

大きな動きでアッパー全体をブラシ掛けしていきます。
ブラッシングによって油分が革へ入り込むサポートをするとともに、余分な油分を革上から取り除けます。
クロスで磨く
ブラッシング終了後は、1日程度靴を静置して革へ油分が浸透するのを待ちます。
………。
はい。
行間はほぼありませんが、1日経ちました。
クロスで余計な油分を拭き取りましょう。

クロスで磨くことをを怠ると、革に残った油分がホコリを吸着。
せっかく与えた油分がホコリに奪い取られてしまいます。
ホコリだらけの靴は見た目にも美しくないですからね。
しっかりクロスで磨きましょう。
オイルドレザー靴の仕上がりを確認
これにてオイルドレザー靴の作業は終了。
仕上がりを見てみましょう。
こんな感じになりました。

革にしっとり感が戻り、ツヤ感も出ています。
作業前後を比較してみましょう。

靴のトゥ(つま先)部分に注目すると、革の色が全く異なることがわかりますね。
ケア前は革の油分が抜けきっていることが遠目からでもわかりました。
しかし、ケア後は乾燥状態であったことなど微塵も感じさせない雰囲気に。
靴ひもを通すと…

格好良いですね。

革がしっとりと、美しい表情に。

縫い目部分も白く、さらに、アッパーの潤い感も十分です。
(2026/02/02 21:59:22時点 楽天市場調べ-詳細)
オイルドレザーにも定期的な栄養補給を
本記事では、乾燥したオイルドレザーの靴に油分を与える方法を紹介しました。
今回はレッドウィングの革靴をケアしましたが、その他のホワイツやダナーなど、各ワークブーツメーカーのオイルドレザー靴も同様の手法でお手入れできます。
ぜひ試してみてください。
いくらオイルドレザーが油分たっぷりで丈夫といっても、メンテナンスしなければ乾燥は避けられません。
乾燥した革はしなやかさが失われ、傷がつきやすくなったり、あまりに乾燥しすぎると割れることもあります。
もちろん、オイルドレザーもその例にもれず…。
オイルドレザーの優秀さにあぐらをかかずに、定期的なケアをしてあげましょう。
お手入れ頻度は他の革靴よりも圧倒的に少なくて良いですけどね。
感覚的には、年に1回程度でも十分。
ちなみに、オイルドレザー靴の普段の日常的なお手入れについてはブラッシングだけでOKです。
基本的にオイルドレザーはラフに、気楽に履ける革靴。
そのため、革への栄養補給はホントにたまにで大丈夫。
それでは、今回はこの辺で。
少しでもご参考になれば幸いです。
ご覧いただき、ありがとうございました!
(2026/02/02 21:59:22時点 楽天市場調べ-詳細)
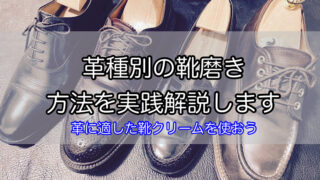
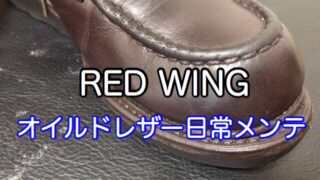
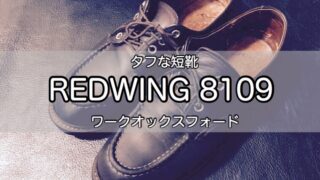


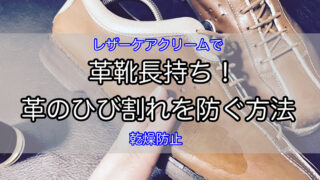
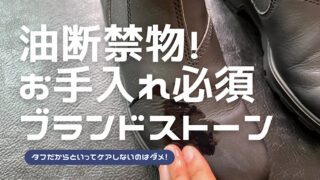

靴磨きを始めたい。けれど道具をそろえるのが面倒…。
そこでおすすめしたいのが靴磨きセット。1セット買うだけで必要な道具がまるっと揃います。道具選びの手間が不要。今すぐ靴磨き可能に。
大事な革靴を劣化させないために靴を磨いてコンディションを整えるのがおすすめです。